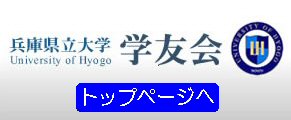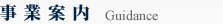|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |


神戸商科大学時代[昭和23年~]

昭和23年 |
新制大学制への移行に伴い、昭和23年4月、県立神戸経済専門学校を改組し、全国最初の公立新制大学として県立神戸商科大学が開学した。 商業経済の研究教育を目指し、従来からの伝統であった 理論と実践とを兼ね備える「商経学部(経済学科・経営学科)」1学部制の単科大学として、大いにその特色を発揮した。 また、昭和25年6月に経済研究所を開所。当時では画期的な共同研究室(海事経済、貿易、経済地理、産業構造、商業英語)を設置して、共同研究の促進を図った。 |
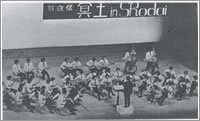
昭和29年 |
昭和29年より「商大祭」が盛大に開催され、以降、学問、文化、スポーツなど過去1年間の大学におけるすべての活動の総決算の場となった。 昭和34年4月、専門技能者を養成することを目的に専攻科(商経学専攻科)を設置、同38年4月には管理科学科を増設した。 また、昭和40年4月に大学院経営学研究科(修士課程)を設置。同42年4月に大学院経済学研究科(修士課程)、同46年4月に大学院博士課程(経営学研究科・経済学研究科)を増設した。 |

昭和46年 |
公立大学の社会的あり方が問われる中、昭和46年7月に 第1回目の公開講座を開講し、同年8月から図書館の一般公開を実施した。
|

平成2年 |
平成2年4月に神戸研究学園都市(現キャンパス)に移転した。 また、平成6年4月、大学院経営学研究科に経営情報科学専攻(修士課程及び博士後期課程)を、同12年4月には大学院経済学研究科経済学専攻(修士課程)、経営学研究科経営学専攻(修士課程)に夜間主コースを増設した。 更に、国際交流として、昭和54年4月からエバーグリーン大学と同60年8月から曁南大学と学術交流を、また、学生交流を同62年9月からエバーグリーン大学、平成12年5月から曁南大学と行い、平成13年度からは、西オーストラリア州立カーティン工科大学とも学生交流を行い、交流の輪を広げた。 |
姫路工業大学時代[昭和24年~]

昭和24年~30年代 |
開学期 県立工業専門学校を母体として、昭和24年4月に姫路工業大学が開学した。 姫路工業大学は「高度なる学問の教授と研究」「人間性の陶冶機関」「職業への専門的修練の機関」の3つを使命とし、国家再建のため工業技術の向上を図り地方産業を発展させる指導的原動力となることを目的としていた。 |

昭和40年代 |
成長期 急激な産業の成長を支援するため、昭和37年 4月に産業機械工学科、同39年4月に電子工学科、同41年4月に金属材料工学科が開設された。 また、同37年4月の産業機械工学科の新設により狭隘となった伊伝居学舎から書写西坂地区へ移転した。 |

昭和50年~60年代 |
充実期 昭和54年7月にキャンパスの文化センターとしての位置づけを持つ新図書館が完成し、完成時点では、西日本の単科大学としては最高の設備をもつ図書館であった。 また、昭和57年に科学技術の進歩に応じた専門分野の深化、高度化、細分化と新技術の開発に対応するため、工学研究科博士課程が開設された。 |

平成元年~16年 |
発展期 単科大学から理工系総合大学へ転換するため、平成2年4月に理学部が開設され、さらに平成6年4月に理学研究科が開設された。 また、県立大学新学部検討委員会の新学部構想に基づき、姫路工業大学と姫路短期大学が統合され、平成10年4月に環境人間学部、同14年4月に大学院環境人間学科が開設された。 |
兵庫県立看護大学時代[平成5年~平成20年]
 |
平成5年4月、国公立で我が国初の看護系単科大学として開学し、教員46名、職員20名の体制で、101人の1期生を迎えた。同年4月15日に挙行された開学式では、河合雅雄氏の記念講演があり、その後ナイチンゲール像の除幕式も行われた。 |

対策本部の設置 |
開学2年目に阪神・淡路大震災が発生した。県立看護大学では、全国的な看護職ボランティアを必要な施設へ派遣し、調整する機能をもった災害対策本部を設置するとともに、全国から駆けつけたボランティアの看護職の方々と避難所での食事や入浴、掃除などの生活支援、また受診などの健康面の相談を受ける活動を行った。 |

大学院入学式 |
平成9年7月2日、関西地区では初めての修士課程となる兵庫県立看護大学大学院修士課程の開学式が行われた。 当日は雨天にもかかわらず関係者230名の出席を得て、式典が行われ、「パラダイムの変革-疾病指向から健康指向へ-」と題したアンジェイ・ポイチャック博士(WHO神戸センター所長(当時))の記念講演が行われた。 |